「外の音、内の香」で書かせていただくようになって、半年が過ぎました。
うきうきとドキドキを胸いっぱい抱えて、一田さんに会いに行ったあの秋の日。吉祥寺のカフェで自己紹介をして、どんな連載にするかご相談して。帰り道、「よし。ひねらず凝らず、明るく淡々と書こう」と決めました。早々にネタ切れになったらどうしようと思っていましたが、毎月楽しく書き続けられています。

一田さんに会いに行った日。いただいた名刺を忘れたり(失礼いたしました…!)傘を忘れたり、駅と逆方向に歩き始めたり。緊張してぽんこつになっていた私。
ただ一つ、ちょっとした悩みが。
紹介する本が、なぜかエッセイや人文書などのノンフィクションに偏ってしまうのです。
私は小説も、エッセイも人文書もビジネス書も、漫画もまんべんなく大好き。せっかく等身大のコラムを書くからには、そのバリエーションをちゃんと紹介したいなと思っていました。しかし、本から得られるものを分かりやく説明しようと思うとつい、ノンフィクションばかり手に取ってしまいます。
働く女性が書いたエッセイを読んで、「わかる!」と共感した。
仕事術が書かれたビジネス書を読んで、「なるほど!」と勉強になった。
貧困問題がテーマのルポを読んで、「知らなかった…」と反省した。
ノンフィクションの特徴はこの、即効性。「読む」と「感じる」にほとんど隙間がなくて、本と自分がつながるスピードが速い。「本を読む目的・意味」が分かりやすい読書と言えるかもしれません。
一方で私は、小説の「遅効性」も愛しています。
小説を読んだ後、「なんだかよく分からない展開だったな…」「面白かったけど、作者がなにを伝えたかったのかはよく分からない…」そんなモヤモヤを感じることはありませんか?
しかし物語の種は、知らぬ間に自分の中に植え込まれています。そして何かの拍子にふと、芽が出る。点と点が繋がる瞬間が訪れて、「あ、あの物語ってもしかしてこういうことなのかな」と腑に落ちたり。何年も経ってから読み返してみたときに、急に「あれ、この登場人物の気持ちがよく分かる…」とびっくりしたり。
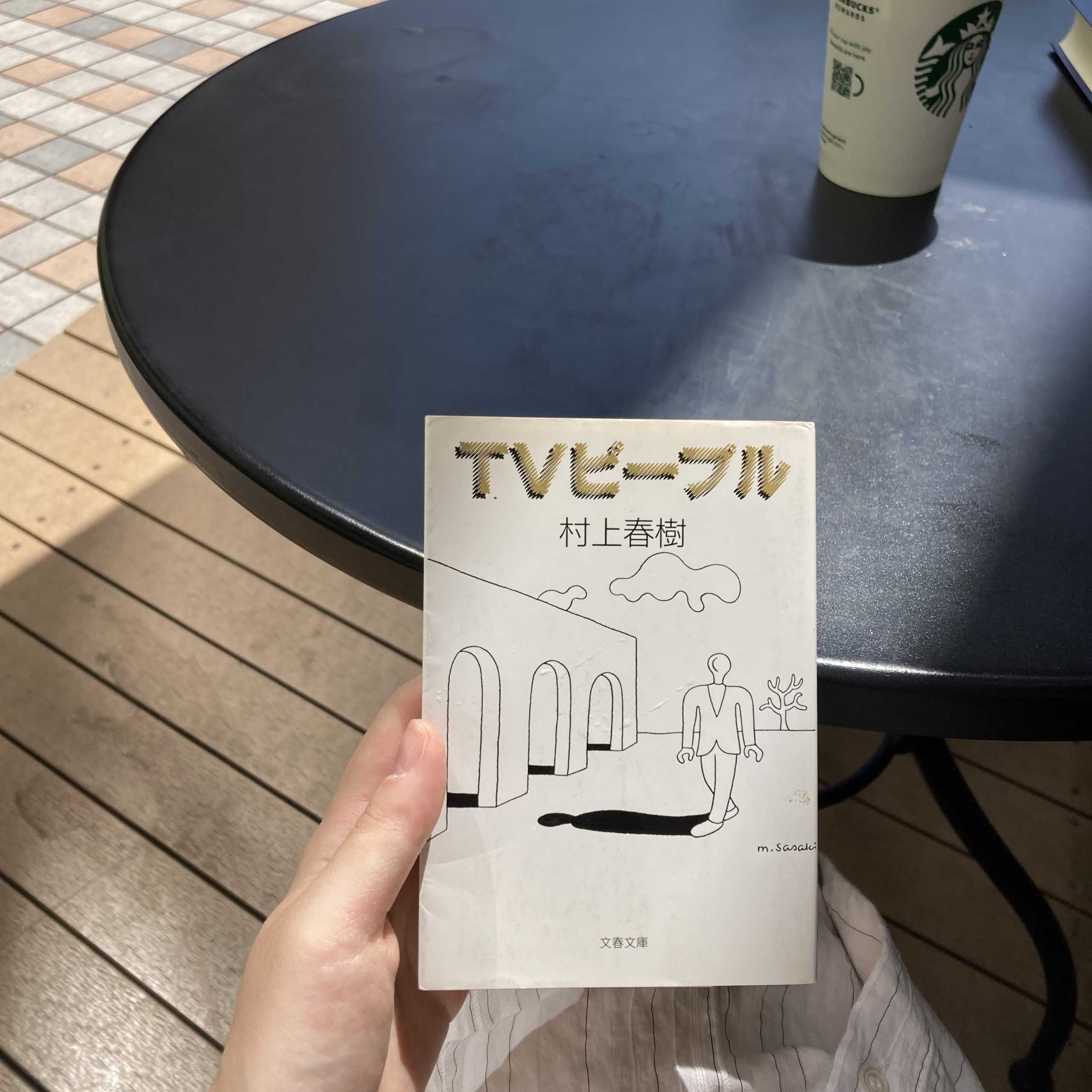
村上春樹さんの短編小説、「眠り」。この作品はまさに、「じわじわ効く」物語です。
初めて読んだのは高校生のとき。平凡な主婦がある日急に眠れなくなり、夜な夜な本を読みながら甘いものを食べ、人生を「拡大」する物語。2週間以上まったく寝ていないのに、身体は健康そのもの。家事も人付き合いもどんどんシステマティックになっていき、学生時代以来の読書に没頭する日々を送ります。
これが本来の私のあるべき姿なのだ、と私は思った、眠りを捨てることによって、私は私自身を拡大したのだ。大事なのは集中力なのだ、と私は思った。――『TVピープル』収録「眠り」より
表向きは完璧な妻・母の仮面をかぶり、一人になるとウイスキーを舐め、チョコをかじりながら読書にふける主人公。
ああ私も、こうやって生きていこう。一応ちゃんとした社会人になるつもりはあるけれど、本来の自分を捨てたりはしない。うまいことやりくりして、「自分を拡大して」やっていこう……。10代だった当時の私は、世間知らずの怖いもの知らず。物語に漂う不穏なムードは意に介さず、ただただ、村上さんの描くクールな女性像に惹かれていました。
この作品は、村上春樹さんの短編小説の中で一番のお気に入り。何度も何度も読み返していましたが、読み方が変わったのは30代を間近にした頃のことです。
体調の変化、複雑化する人間関係、どんどん重くなる仕事の責任、でも好きなこと(読書)は諦められない……。そんな状態で読み直す「眠り」は、最初から最後まで徹底してホラー小説でした。周囲の人と正面から関わること、社会的責任、自分のケア・休息。そんなものをすべて「余計なこと」と放棄して、自分のエゴに集中してしまう危険。
もし死というのがこういうものだったら、私はいったいどうすればいいんだろう。死ぬということが、永遠に覚醒して、こうしてじっと暗闇を見つめていることだとしたら?――『TVピープル』収録「眠り」より
本を読みながら夜が明けてしまった朝。はっきりしているのかぼんやりしているのか曖昧な頭に浮かんでくるのは、「●時間睡眠が健康的」といったノウハウ本の一節ではなく、「死は眠りの先ではなく、覚醒の先にあるのでは?」と恐怖に震えていたあの女性のこと。「眠り」が私に埋め込んだ種は、皮膚の下に入り、肉や骨を分け入って、とても深いところに根づいているようです。
フィクション・つくりものを読んで、なんの意味があるんですか? なにが得られるんですか? そんな疑問を持つ人は少なくないと思います。「小説を読む」ことが、なんだか子供の遊びのように感じられる人もいるのかも。
「分かりやすさ」「効率性」「コスパ」の点では、小説は劣等生かもしれません。しかし、「読んだときすぐには分からなくても、いつの間にかじわじわと効いていることに気づく」のが、小説の面白さ。
自分の中に植え付けられた「物語の種」が、時限爆弾のように芽吹きのときを待っている。そんな風にイメージしてみたら、なんだか面白そうでしょう? 普段あまり小説は読まないなぁという方も、ぜひだまされたと思って、なにか一冊手に取ってみてください。

GWに、芝パークホテルでお茶してきました。こちらには、蔦屋書店が監修しているライブラリーラウンジがあります。アフタヌーンティーにも、本好きの心をくすぐる仕掛けがたくさん。紅茶につかうお砂糖と砂時計が、本の形をした箱に入って出てきました!

